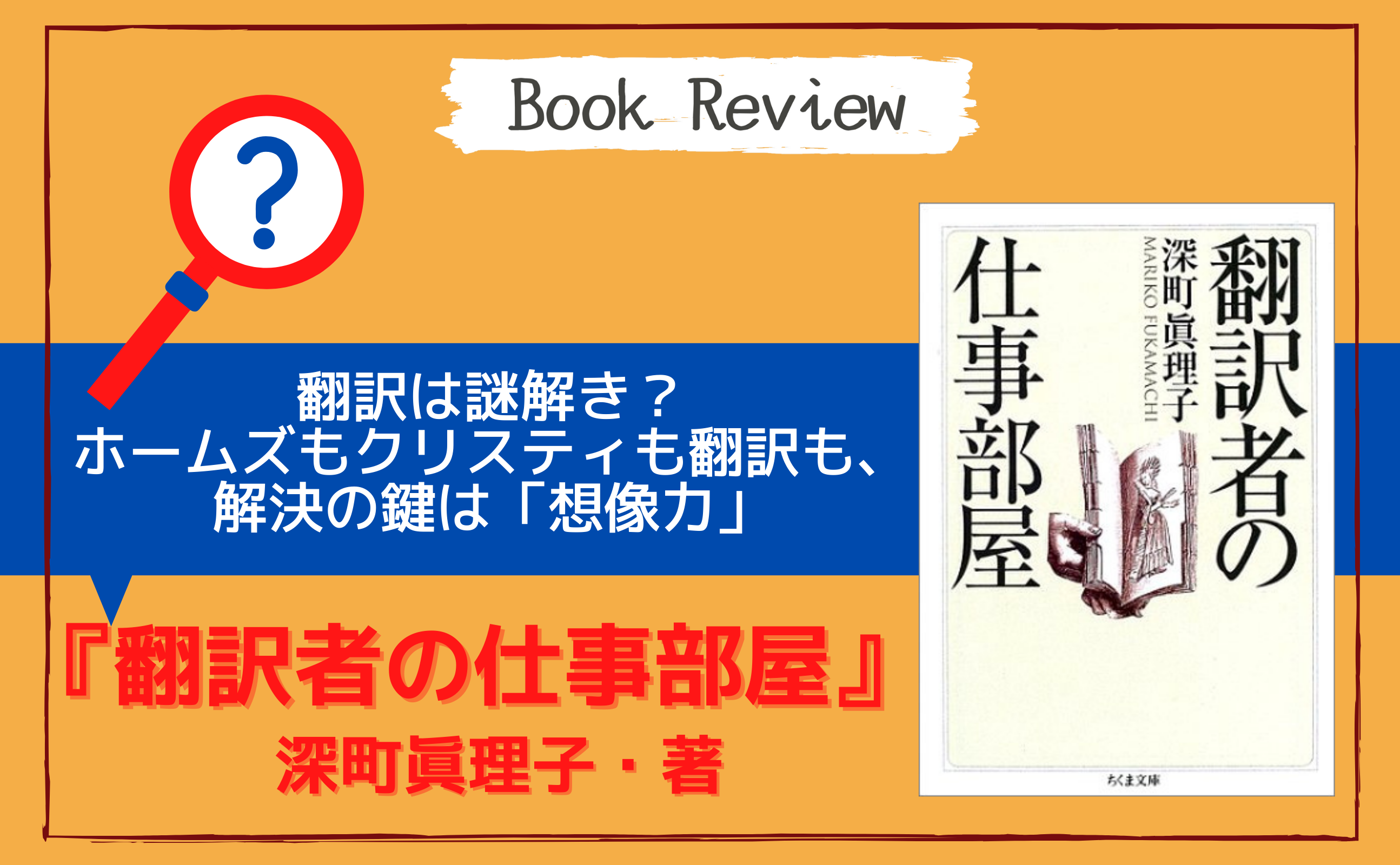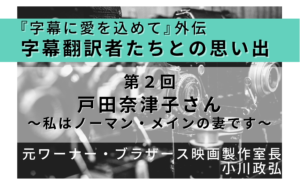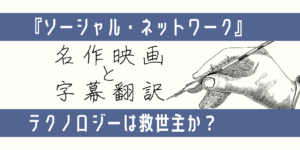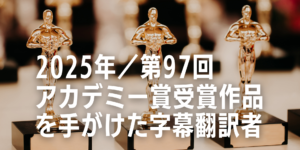本書のタイトル『翻訳者の仕事部屋』。ここからどんな内容を想像するでしょうか? もしあなたがそのタイトルから「著者の書斎や、そこに置いてあるものを紹介した本かな」と考えたなら、少しばかり想像力が足りないかもしれません。
この本は、出版翻訳業界の大ベテラン翻訳者である深町眞理子氏が、翻訳という仕事や大好きな読書、またその日常生活についての様々なエピソードをつづったエッセイです。著者がこれまでに翻訳を手掛けた書籍は『アンネの日記』(新訳版)ほかジャンルを問わず多数ありますが、特にミステリーには造詣が深く、アガサ・クリスティー、コナン・ドイル、スティーヴン・キングなどの作品も多く担当しています。
本書からまず伝わってくるのは、著者が大の読書好きということ。幼い頃は友達の家に遊びに行っても「何か本はない?」と言って本を読み始めてしまい、友達のひんしゅくを買うような子供だったそうです。特にミステリーは別格で、たくさんの証拠をひとつひとつ拾い集め、論理に基づいて推理し結論にたどりつく、というのがたまらなく好きなのだそう。本書の中でもこれまで著者が読んだ本、訳した本が、独特の深い視点から魅力的に多数紹介されていて、読書の楽しさを思い出させてくれます。
その読書好きが高じて翻訳者になったそうですが、逆に「本を読むことと文章を書くことが好きでなければ、翻訳のプロとしては長続きしない」とも述べています。翻訳者の必須条件といえば、一般的にまず挙げられるのが“外国語の読解力”と“日本語の表現力”。当然、著者もこの2つのどちらが欠けても欠陥翻訳にしかならない、と言っています。しかしその2つの絶対条件に加えてとても重要なのが「想像力」であり、その想像力を養うのに非常に効果的なのが「本を読むこと」だというのです。
では、翻訳にはなぜ想像力が必要なのでしょうか。その理由は本書の中でいくつか述べられていますが、ひとつは翻訳者にとって一番避けたいものである「誤訳」。誤訳の原因は単純な単語の意味の取り違え、背景知識の不足など様々ですが、著者は想像力によって、これらの大半はなくせる、と言います。
私自身は皆無とは言わないまでも、誤訳はごくすくないと自負しているが、これは何も、とくに語学力がすぐれているわけでも、背景知識が豊富だからでもない。想像力を用いることで、これでは意味が通らないとか、どうもへんだ、なにか足りない、といったことに気づくだけなのだ。
これは字幕ディレクターの仕事をしていると、本当にその通りだなと思います。ドラマの字幕をチェックしていると、英語は何も耳に入ってきていないのにもかかわらず「この部分、何かがおかしい。つじつまが合わない」と思うことがよくあります。そして英文を確認すると、たいていそこに何かしらの誤訳やカン違いが眠っているのです。
単語の意味というものは1つではありません。例えば誰もが知っているcompanyという単語。辞書も引かずに「会社」だと分かる方がほとんどでしょう。ですがこの単語には「仲間・友人」という意味や、軍隊においては「中隊」という意味など、多くの意味を持ちます。機械的に英文と訳語を照らし合わせると一見正しい訳のように見えても、誰が、どういう状況でその単語を発しているのかを想像し、何かおかしいと感じることができれば、その英単語に他の意味がある可能性や、文章全体が慣用句でまったく別の意味である可能性に気づくことができます。特に映像を伴う映像翻訳においては、物語の背景や状況に加え、役者の表情や話し方まで見て推察しないといけないわけですから、なかなか大変です。
しかし著者の深町氏はそんなふうに常に想像力を働かせて翻訳をすることを心から楽しみ、分からない部分が分かった時こそが翻訳の喜びだと言います。
私にとっては、翻訳もいわば謎解きの一種だ。たとえば、原文にはたんに“He smiled”とあっても、こういう性格の彼なら、こういう場面で「にっこりした」のか、「にんまりした」のか、あるいは「にやりとした」のか、それを類推するのがおもしろい。
難解な翻訳に当たった時や作業が思うように進まない時は、仕事に取りかかるのが億劫になりがちです。ですが本書を読むと、“翻訳は壮大な謎解き”だと感じられるでしょう。そんなふうに捉えると難しい翻訳も、まるでこれからクリスティのミステリーを読み始める時のような、わくわくした気持ちで取り組むことができるかもしれません。
【執筆者】
梶尾佳子(かじお・けいこ)
フリーランスの字幕ディレクター兼ライター。日本語版制作会社の字幕部にて6年勤務した後、独立してフリーランスに。翻訳を含め、言葉を扱う仕事に関する様々な情報や考えを発信していけたらと思っています。